「食文化の豆知識」カテゴリーアーカイブ
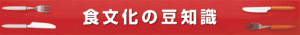 |
| |
| 【第26回】 [ 食環境の現状(5) ] |
| |
| “ブルータスお前もか”と言いたくなるような食品偽装事件が、またも誌面をにぎわせています。京阪神を中心に高級食材取り扱いで知られるスーパーマーケットで販売された冷凍コロッケに、偽装表示があったというのです。実際はホルスタイン種の牛ミンチを使いながら”和牛肉使用”と表示していました。明らかなJAS法違反です。このスーパーでは今年4月にも干し椎茸の産地偽装で厚労省の指導を受けています。ただ、擁護するわけではないのですが、コロッケに和牛を使用していた時期もあり、引継ぎミスによりホルスタイン種に変えた後も表示が和牛のままになってしまったと主張しており、それが事実であるならば先のミートホープ社のような悪辣さは少ないような気がします。故意なのか過失なのかの見極めは難しいところですが、1日も早く信頼を早く回復して欲しいものです。 |
| |
| 2002年の雪印食品の牛肉偽装事件に端を発した一連の偽装事件は、とどまることを知らず、発覚の頻度も高くなっています。安全への関心、厚労省の監視体制強化、そして何よりも内部告発が、大きく発覚をうながしていると思われます。今後も食品偽装のさらなる発覚は覚悟しておいたほうが良さそうです。 |
| |
| 食品偽装の歴史?をみるに、牛肉がらみ事件が多くを占めています。和牛と輸入牛との価格差、ブランド和牛に対する絶対的支持、などが偽装を誘発しているといっても過言ではありません。輸入牛を国産牛と偽っていた雪印食品事件は、国産牛BSE感染牛確認による国産牛買取り補助金狙いが目的でしたが、最近の偽装は輸入牛を和牛と偽ったものです。その逆はめったにありません。確かに和牛は日本人の口に合う美味しさがあります。でも品質に照らしてもあまりにかけ離れた価格差には、もっと消費者が怒る必要もあるかもしれません。末端価格の高さには、諸事情があるのはわかりますが、”何が何でも和牛ブランド”の思い入れが、価格を必要以上に押し上げている可能性は否定できません。 |
| |
| 牛肉業界関連の度重なる偽装事件を完全になくすことは簡単ではありませんが、行政による監視体制の強化や、消費者の厳しい目、偽装会社への厳しい罰則等による抑制継続が必要です。そして、誤解を恐れずに言えば、牛肉価格安定のための潤沢な供給システムへの道筋を急ぐことです。 |
| |
|
| |
| |
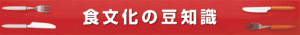 |
| |
| 【第25回】 [ 食環境の現状(4) ] |
| |
| 世間を震撼させた牛肉コロッケ偽装発覚事件では、北海道県警が不正競争防止法違反で捜査に乗り出しました。今後は司法の手にゆだねられるでしょう。ほっと一安心もつかのま。今度は大阪の仕出し弁当製造会社が、賞味期限をはるかに超えた冷凍食材を使用していたことが保健所の調べで分かりました。倉庫に保管されているミートボールなどの冷凍食材約50品目も期限が切れており、中には、期限切れから2年9ヶ月にもなる冷凍の厚焼き卵もあったとか。 |
| |
| 一方で、水産大手の子会社である食品会社が、賞味期限切れ原料入りのネギトロ用マグロを出荷していたことが分かりました。回収に乗り出しましたが、大半は消費されてしまっているとのこと。漁獲量規制などによりマグロ価格が上昇した為、賞味期限切れの加工済み冷凍マグロを原料に混ぜ続けていたのです。 |
| |
| どちらも、コストを抑えるために日常的に行われていた許されない所業です。健康被害が今のところ出ていないのが幸いです。調合や味付けでうまくごまかされたこれら食品が賞味期限切れであることなど、消費者には分かるはずがありません。だから、どちらも長きにわたって続けてこられたのでしょう。成分表示を見て判断できる選食力もこれには役には立ちません。 |
| |
| 賞味期限切れの食品で、思い出したことがあります。実母の引っ越しを手伝っていたとき、食品庫から数品の缶詰が出てきました。そのひとつの賞味期限を見ると、なんと12年前の表示が。これにはこけそうになりました。即、捨てましたが、分からずに食べていたらどうなっていたか不明です。少々の期限切れは、体調に影響を与えるものではないと思いますが、業者が確信犯的に使用してはならないことです。 |
| |
| 賞味期限切れ使用食品を消費者が見破るのは困難ですが、成分表示はある程度見極めることは可能です。ある新聞に、成分表示の信頼性を問うアンケート結果がでていました。95%以上の人が、表示の規制や検査を強化すべきだと答えているのは当然として、現状の成分表示情報を信頼しているか否かは、ほぼ5割づつに分かれました。加えて、成分表示より価格を購入の判断材料にする、という人も半数を超えていました。悩ましい結果です。厳しい規制での表示をほとんどの人が強化すべきだと思う一方で、購入する時に優先させるのは成分表示より価格だというわけです。そこに諸事情が透けて見えるような気がします。 |
| |
|
| |
| |
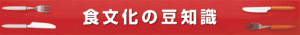 |
| |
| 【第24回】 [ 食環境の現状(3) ] |
| |
| 次から次へと誌面をにぎわす食の不祥事。とりわけ今回の北海道の食肉加工会社がしでかした豚肉や鶏肉を混ぜたひき肉を[牛100%]として出荷していた偽装事件は、確信犯的犯罪行為といえるでしょう。 |
| |
現時点での容疑は、不正競争防止法違反にあたるとか。原産地や品質、数量などを不正表示して商品販売することを禁じる法律に違反したという容疑です。
根っこは、安い原料費で高く売らんがための原始的で単純な詐欺行為ですが、腐臭を発するような豚肉を仕入れたときには、殺菌処理を施した上に、牛肉らしく見えるよう家畜の血液で赤く着色して使用したこともあると聞けば、食の安全にもかかわってくる問題で、まさに噴飯ものです。豚肉大好き人間としても許せません。 |
| |
| そこで、問題の食肉加工会社の社長が放った捨てセリフとでもいうべき[この業界全体の体質の問題で、スーパーでなぜ冷凍食品の半額セールができるか考えて欲しい。うちも悪いが喜んで買う消費者も悪い]との発言。責任転嫁する発言だと批判が相次いだため、すぐに発言を撤回し謝罪しましたが、この発言は本人の本音を見事に表しているに相違ありません。24年もの間、罪の仮借もなく日常的に不正が行われてきた原点が、そこに見えるからです。 |
| |
| 確かに大半の消費者は安いものを求めますが、一応の信頼の上での購入が成り立っており、安いからといって、豚肉を牛肉と偽ったものを売って許されるわけはありません。でも、何故こんなに安いのか、こんなに安く売れるのか、を疑ってかかるのも、必要であると思うのです。今回のような業者向けの卸業者の偽装は、末端利用者である消費者が用心して回避できるものではありませんが、何故、こんなに安いの?の疑問から、その食品の原材料、原産国、様々な添加物等をチェックしてみるのも一法です。 |
| |
| 今回の偽装事件を受けて、日本農林規格(JAS)の品質表示基準の見直しが検討されています。従来、JAS法は消費者に販売されている食品を対象としたものですが、それを食品卸業者にまで広げようというものです。後手後手に回る法の整備ではありますが、悪質きわまりない偽装発覚がもたらした、”食の安全”への信頼回復の制度改正となりそうです。 |
| |
|
| |
| |
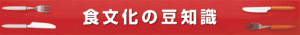 |
| |
| 【第23回】 [ 食環境の現状(2) ] |
| |
| 食品添加物がどのように使われているか、その怖さも便利さもを併せて克明に記した上で消費者の意識改革を啓発する出版物が、60万部以上を売るベストセラーになっているとか。食品添加物商社に勤務されていたという著者の臨場感あふれる記述は、安い食品を大量に作ることを第一義としがちな食品業界の裏側や、それを歓迎する消費者への警告が読み取れて、食選力の重要性を考えさせられる内容に仕上がっています。 |
| |
| はからずも最近、相反する主張を目にする機会を得ました。ある新聞の食関連記事に「このところ、無添加のアピールが目立つが、消費者の不安を背景にしたいい加減な表示は慎むべきだ。また良質な製品作りに欠かせない添加物もある。熟成ハムやソーセージに使用される亜硝酸塩は食中毒菌を抑え、風味を良くするには不可欠である・・」とあり、無添加などを強調した表示が、かえって不安や誤解を助長している側面もあるので、消費者もきちんとした知識を持って良い選択をすべきだ、という内容でした。もっともな主張ですが、亜硝酸塩のくだりが少し気になりました。ハムなどに使用される亜硝酸塩は、アミン酸を含むものと一緒に食べれば、胃の中でニトロソアミンという発ガン性の疑いがある物質が作られる可能性があることは、一般にも知られているからです。 |
| |
| そして、ハム・ソーセージ作りの二業者のホームページを見ました。有名なハム関連会社では、「亜硝酸塩は一般細菌の増殖を抑え、ポツリヌス菌の増殖も抑え、肉色素の酸化を防止し、脂肪の酸化も抑え、獣臭を消し、香ばしいハムの風味を醸し出す」と、まさに良いことづくめです。逆に、亜硝酸塩を使わずに作ったハム・ソーセージにはポツリヌス中毒のリスクがあり、欧州では発色剤(亜硝酸塩)を使わない自家製ハムなどで死者も出ている、と主張しています。 |
| |
かたや、20年前から無添加のハム・ソーセージ作りに取り組んでいる会社。
亜硝酸塩がハム作りには欠かせないという世界の常識を乗り越え、実験を繰り返しながら無添加の製品作りに挑戦しています。新鮮で上質の黒豚肉100gを使うと70~80gのハムが作れるとか。ただ発色剤を使わないので茶色い色をしています。砂糖や香辛料のみの漬け込み液で、肉のくさみを減らし美味しく仕上げる努力を続けています。
一方、市場に出ている多くのハム・ソーセージ会社のものは、冷凍の輸入豚肉を使用し、リン酸塩などの結着剤を加え、大豆タンパクなどを増量することで肉100gから120~130g程度作れるようです。 |
| |
| いまは、安全とされる添加物も、明日には危険メッセージが出されるかもしれません。厚生労働省は万全な守り神ではあり得ないのです。 |
| |
|
| |
| |
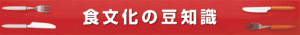 |
| |
| 【第22回】 [ 食環境の現状(1) ] |
| |
| スーパーマーケットやデパートで見る和牛の価格の高さに、ため息をついていたこの3月、農林水産省は、「和牛」と表示出来るのは、日本生まれで日本育ちの牛に限ると決めました。「国産」は、輸入物でも日本で育った期間が最も長ければ表示できます。一方「和牛」も、日本固有の黒毛和種、褐毛和種、日本単角種、無角和種およびこれら4品種間の交配雑種であれば、輸入物でも和牛と表示できました。ところが、これからは、黒毛和種牛であっても、輸入品はそうは記載できないことになります。今回の表示規則は、日本産のいわゆる和牛のブランド化による付加価値アップを狙うための決定と思われますが、結果としては、日本の畜産業者を守り、美味しい和牛を食べるためには消費者に高い金額を課せることになるのではと懸念されます。 |
| |
はからずも、米国産牛肉の輸入条件緩和の見通しが立ってきました。現在、生後20ヶ月以下の牛の肉に限定している条件を、30ヶ月以下に緩和する動きが見られます。和牛と明らかに肉質が異なる豪州産牛肉と違い、米国産牛肉は和牛の種牛や遺伝子をもとに、日本人好みの美味しさを持つものが、多く飼養されています。以前に行ったある焼き肉店のこと。食通の人に紹介されたのですが、評判通り美味でジューシーで肉の旨みがとろけ出すような、絶品の肉でした。お値段もなかなかのものでしたが、皆とても満足しました。ところが最近、その店が閉店したとのこと。なんと、その店は米国産輸入肉をメインに取り扱っていたため、長引くBSEによる輸入規制に耐えきれなくなったのです。
てっきり、国産の和牛とばかり思っていました。 |
| |
いま、米国産牛肉の輸入量は、禁止される前の10分の1程度だといいます。
よって、美味しい牛肉を食べようとすると、純国産牛100グラム1000円前後以上は覚悟しなければなりません。米国産牛肉の輸入禁止が、和牛価格をますます押し上げています。勿論安全第一ではありますが、100万頭に1頭より低い水準(米農務省)というBSE有病牛を食して、10数年後に牛海綿状脳症を発症する確率は、いかほどのものでしょうか。
日ごろより、国産にこだわっている筆者ですが、目玉の飛び出るほどの和牛の高さに、いささか辟易しているこのごろです。 |
| |
|
| |
| |
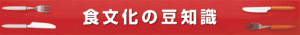 |
| |
| 【第21回】 [ 食育の重要性(7) ] |
| |
手軽に楽しめる娯楽としての外食。娯楽の雄である旅行とはまた異なり、少しの時間があれば充分楽しめるのが、大きな魅力です。
需要拡大を受けて、外食は子供の世界にいたるまで日常にすっかり定着してきました。ちょっと前までは、ハレの日か、外食慣れしている大人が利用してきた寿司店。いまでは回転寿司店が軒を連ね、多くの日本人の食生活にとけ込んでいます。ちょっと気を張って寿司店ののれんをくぐる。子供などは連れて行ってもらえない。そんな寿司のイメージを見事に大衆化したのは、回転寿司店の手柄?ではありますが、なんだか、食文化そのものが、味気なくなってしまったように感じませんか? |
| |
| 好きなときに、好きなだけ食べられる。しかもそこそこの値段で。これが、回転寿司店の人気の理由でしょう。“好きなだけ食べられる”、は、他に、バイキング形式や焼き肉食べ放題手法などを増長させてきました。かつての高級な料理が、雨あられのように落ちてきて、大衆化の形となって食卓を豊かにうるおしています。それらを拒否するものではありません。回転寿司も、市場に登場した頃と比べるとずいぶんと品質もアップし、専門店にひけをとらないネタ揃いも珍しくありません。競合店が多くなり、差別化が必要となったためでしょう。歓迎すべきことです。 |
| |
| でも、回転寿司に馴染んだ子供が大人になった時、ちょっと小粋で、板前が“今日はいい○○が入ってますよ。にぎりましょうか”と声をかけてくれる専門店に、果たして自分の金で行くのでしょうか。そこには、大人だけが味わえる、ちょっと緊張する空気が流れる。客と板前のコミュニケーションが、料理に香り付けをしてくれるのです。その極上の食を楽しめるのでしょうか。 |
| |
好きなだけ食べる、という食べ方が、大きなうねりとなっているようです。
あるホテルのランチバイキング。大人3500円で、何と100種類以上の料理が食べ放題。開店前に人が列をなしていました。確かに、好きなだけ食べられる。そこでは、上質なものを丁寧なサービスで味わうといった、落ち着いた雰囲気は望めません。でも、“好きなだけ食べられる。そこそこの値段で”。
そのうち、フランス料理食べ放題、ふぐ食べ放題の店も冗談ではなく登場しそうです。はじめは、ちょっとうれしいかもしれません。 |
| |
| 食生活は、時代によって変化していくのは当然です。でも、継承していくべき食習慣は歴然とあるのです。食文化とは、食材に対する敬意と、作ってくれた人に対する感謝から、生まれるものではないでしょうか。 |
| |
|
| |
| |
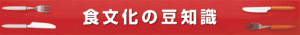 |
| |
| 【第20回】 [ 食育の重要性(6) ] |
| |
|
外食が日常の楽しみとして定着している昨今、昼食利用でのそれは、必要にかられて、というケースがあるようです。ウオーキングパーソンにとって昼食は楽しみと同時に、面倒なことでもあるからです。時間の制約、店の混雑状況、予算の関係などなどが、ゆっくりと好みのものを快適な状態で取れるような昼食タイムの実現を、難しくさせています。自宅から弁当持参がベストなのでしょうが、それぞれ事情があって、そういうわけにもいきません。結果として、オフィス街の昼食時にはコンビニエンスストア等で弁当類を買い求める人であふれています。手軽な価格で購入でき、会社で食べることが出来る。中食と呼ばれる弁当類は、働く人々にとって、とても便利なものです。成長市場として期待されているのも無理からぬことでしょう。
|
| |
|
先日の昼食時のことです。よく利用する麺類の店が満員でした。出汁がなかなか旨い店で、いつも混雑しています。で、近くのコンビニエンスストアで、何か仕込むことにしました。まず一店舗目、美味しそうな巻き寿司が目に付きました。どれどれと、イヤな性分から裏の表示ラベルを拝見。そこには次のような表示が。「すし飯、卵焼き、そぼろ、海老、かんぴょう、きゅうり、かまぼこ、のり、食酢、砂糖、調味料(アミノ酸等)、ソルビン酸カリウム、ステビア、甘草、香料、乳化剤、ソルビット、グリシン、 PH 調整剤、ペクチン化合物、酸化防止剤、凝固剤、増粘多糖類、赤色3号、赤色106号、コチニール、カラメル、カロチン・・・」ちょっと違っているかもしれませんが、そのような表示でした。思わず、店頭棚に返しました。
|
| |
|
次の店で、昆布おにぎりを手に取りました。シンプルでいいのではないかと思ったのです。表示はといえば、「白飯、昆布、醤油、砂糖、調味料(アミノ酸等)、 PH 調整剤、グリシン、カラメル、増粘多糖類、ソルビット、甘草、ステビア、ポリリジン・・・」。そっと戻して、さらに次の店に行きました。コンビニエンスストアの激戦区なのです。そこにあった“おむすびと田舎煮のお弁当”。裏の表示を見れば、「かやくご飯、鯖塩焼き、卵焼き、ひじき煮、味付け海苔、ごま、調味料(アミノ酸等)、 PH 調整剤、グリシン、キシロース、甘味料(アセスルファム K )カラメル色素」となっています。そろそろお腹も空いてきたし、時間もなくなってきました。少しは添加物が少ないような気もします。そこでこの弁当で妥協することにしました。
|
| |
弁当は、まずまずの味でした。各コンビニエンスストアでも、添加物に無頓着なところもあれば、一応、保存料と着色料無添加を謳っている店もあります。
何を選ぶかは、全く利用者の裁定にゆだねられているのです。 |
| |
|
| |
| |
 |
| |
| 【第19回】 [ 食育の重要性(5) ] |
| |
|
過去に例が無いほど“健康”に関する情報が飛び交っている状況下、またもやあるテレビ番組でねつ造が発覚しました。正確なデータや裏付けも無いままに、あたかも、特定の食品の効能が医学的に証明されたかのように放映されたのです。次の日にはスーパーで売り切れ状態であったとか。その後のかまびすしい騒ぎは、衆知の通りですが、“情報を鵜呑みにするな”という教訓は与えてくれたようです。誤解を恐れずに言えば、特にテレビで流される情報は、信憑性をまずは疑ってかかるのが賢明と言えそうです。(テレビ局在勤経験のある知り合いの人よりの提言です)
|
| |
|
自分の目を、舌を、鼻を鍛錬し、偽物を見分ける能力:選食力を身につけないということは、自分の健康をひとまかせにするということにつながるのです。怖いことだと思いませんか?
出来る限り本物の食材を使ってがんばっている飲食店でのこと。刺身に添えられた本ワサビを見て、“このワサビ、色が悪いな”と若い男性が小声で言うのを耳にしました。その人は多分日ごろより、着色料たっぷりの色鮮やかな即席ワサビしか、口にしていなかったのでしょう。
|
| |
|
何も、高い食材ばかり使用する必要もないし、高級店ばかり行くこともありません。ただ、大量生産され、賞味期限が切れれば捨てられる弁当類やファストフードが、それでも低価格で出回っていることの意味を考えたいのです。商売だから、採算のとれる価格に設定してあるはずです。となると、どのような素材が使われているのか、日持ちを保つために何が添加されているのか。
|
| |
|
 ある店でサンドウイッチを買って新幹線内で食べたことがありました。急いでいたのと食べやすさに惹かれてのことですが、多分もう買うことはないと思います。妙な味がしたのです。腐ってはいないけれど、明らかに素材以外の何かの味が後味の悪さにつながったのです。だれでもが知っている大手メーカーのものでした。一方で、わざわざ遠回りしても買いに行きたくなる美味しいサンドウイッチに出会ったこともあります。フレッシュな野菜に上質のハム、玉子やパンプキンコロッケなど、バラエテイ豊かな品そろえで、本物の味わいがうれしい。知人に勧めても、総じて好評です。 ある店でサンドウイッチを買って新幹線内で食べたことがありました。急いでいたのと食べやすさに惹かれてのことですが、多分もう買うことはないと思います。妙な味がしたのです。腐ってはいないけれど、明らかに素材以外の何かの味が後味の悪さにつながったのです。だれでもが知っている大手メーカーのものでした。一方で、わざわざ遠回りしても買いに行きたくなる美味しいサンドウイッチに出会ったこともあります。フレッシュな野菜に上質のハム、玉子やパンプキンコロッケなど、バラエテイ豊かな品そろえで、本物の味わいがうれしい。知人に勧めても、総じて好評です。
|
| |
|
食に関する商売で、“志”を欠くことのもたらす弊害は、後を絶ちません。巷間をにぎわしているお菓子メーカーしかり。素人が判断不可能な例もありますが、“質”を見極める力を、消費者が育ていくことが、この業界の底上げにつながっていくと思うのです。
|
|
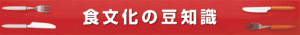 |
| |
| 【第18回】 [ 食育の重要性(4) ] |
| |
|
今の日本では、体に良いもの、すなわち安全で滋養があって新鮮なもの、を食べることは難しいことではありません。予算に応じて、きちんとした食生活を送ることは、だれもが十分に可能です。大根 1 本と厚揚げが、ファストフードでのハンバーガー&ポテトフライより高いわけではないのです。
予算が潤沢にあれば、新鮮な素材を用いてバラエテイ豊かな料理を食べさせてくれるレストランで、豊かな食事を楽しむことも出来ます。
|
| |
|
生活習慣病としてのメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に、警鐘を鳴らす声がさかんに聞こえてきます。高血圧、中性脂肪、糖過多などは、いずれも喫煙、アルコールとともに、食生活が大きく影響しています。人間のエネルギーの源は“食”なのですから、当然のことでしょう。そして食べることに深く関与している“腸”。その腸は、人間の免疫の60%をしめていると言われます。体に良いもの、体が喜ぶものを食べることで、腸を丈夫にし、強い体を形成していくことはとても大切なのです。
|
| |
|
「ただ、子供の食生活は、自己責任に帰する大人と違って、親を中心とする周りの大人の責任に負うところが大きいのが問題です。甘い炭酸飲料をたっぷりと飲み、コンビニエンスで菓子パンとスナック類を買い食いし、家では肉系の料理ばかりを与えられた子供が、どんな体の大人になるのか、すでに結果が出始めています。子供の体力の低下や若年性糖尿病罹患率の上昇。肥満度も高くなっています。
|
| |
|
早急に求められるのは、どんなものを食べると安全なのか、健康になるにはどんな食べ物が必要なのか、を見極める能力です。望ましい食生活とは、決してストイックなものではありません。“安全で新鮮なものをバランスよく、適量食べる”ことがポイントなのです。
|
| |
|
まず、大人が選食能力を持つことで、おのずと子供の食生活が良い方向へと向かっていきます。ある店で見た光景。親が8種類ものドーナッツをトレーに載せて歩いている後ろから、同じくらい載せてついていく子供。店内での食事です。親子供とも超肥満体型でした。別に人に迷惑をかけているわけでもなし、好きなものを食べて何が悪い。ほっといてくれ?の声も聞こえてきそうですが、やはり、偏った食生活によって生活習慣病になるのは避けたいものです。
健康寿命が伸びてこそ、いきいきと生活できるのではないでしょうか。
|
| |
|
| |
| |
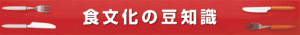 |
| |
| 【第17回】 [ 食育の重要性(3) ] |
| |
|
食育には、味の見分け方、鮮度の判断力などに加えて、「食べる」動作の教育も含まれます。それも早い時期からの習得が望まれます。なぜなら、食事のマナーはその人の成人度を図るめやすにもなる重要なファクターでもあるからです。
|
| |
| 最近、学校の給食時に“いただきます”の挨拶をしない子供が増えているという記事を見かけます。理由はというと、“ちゃんとお金を払っているのに、何故いただきますと言わなくちゃいけないの?”と、親も子供もそろっての理屈が聞かれるとか。にわかには信じがたい話ですが、もし本当なら、その子の将来を案ぜざるを得ません。食事のマナーの原点は、食材や作ってくれた人への感謝や周囲と調和する心にあるからで、それを習得出来ないままに大人になる不運が案じられるからです。 |
| |
|
「食べる」という行為をずっと一人で行う人生を歩む覚悟があるなら、またマナーなど必要でない場所での食事に徹するというなら、どんな食べ方でも自由でしょう。確かに、食べるということは本来、原始的な行為であり、人間も手づかみの長い時代を経て、各国それぞれの食事マナーを形成してきたのです。そして、今必要なのは、堅苦しい作法を細かく習得することより、マナーを通じて、「食」への感謝を育てていくことでしょう。
|
| |
|
食事の基本的作法は家庭でしつけられるべきものです。箸の使いかた、肘をついて食べないこと、ご飯とおかずは交互に食べること等々、各家庭できちんと、教えられているのでしょうか。食べる前には必ず“いただきます”。食べ終わったら“ごちそうさまでした”が当たり前のこととして浸透することが、マナー習得の出発点であるはずです。
|
| |
|
海外に行ったことのない人はいても、外食をしたことが無い人は、まず見かけません。外食時のマナーは、うどん店、牛丼店、ファミリーレストラン、デイナーレストラン etc によって異なるのは当然ですが、きちんとしたテーブルマナーを身につけてこそ、気軽な店でもそれ相応に食を楽しめるというものです。
その逆はあり得ません。芯からマナーが身に付いていないと、大衆的な店で気持ちよくきれいな作法で食べるのは実は難しいことなのです。
食事のマナーがきちんとしていることは、人間にとって大切な財産であるといえるでしょう。
|
| |
|
| |
| |

