「食文化の豆知識」カテゴリーアーカイブ
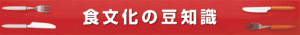 |
| |
| 【第16回】 [ 食育の重要性 (2) ] |
| |
| 昨今の、消費者の食の安全に対する関心の深さや本物志向を受けて、食を提供する側でも、“本物の味”“こだわりの○○”といったキャッチをつけて販売するケースがよく見られます。確かにアピール度は高くなります。しかし原材料を眺めれば、ごく一般的な食材であったり、いろいろな添加物が入っているといった場合も少なからずあるのです。そういった風潮を苦々しく思う人たちの中から、“本物という言葉を軽々しく使うことが間違っている”“果たして本物って何だ?”という声が聞こえてきます。 |
| |
| 「本物」とは、いったい何をさすのでしょうか?簡明に判断するのは非常に難しいのですが、確かに言えることは“余分なものが加えられていない食材であること”が、本物の条件のひとつであるということです。 |
| |
| 毒々しい着色料のついたお菓子、旨みを添加した即席みそ汁、きれいな色合いのハム類、すぐに悪酔いしてしまうお酒、甘すぎるチョコレート等は、見かけをよくするために、口当たりを良くするために、日持ちを長くするために、または作るコストを押さえるために(これが大きな理由の一つ)、本来の食材に、いろいろな安価な成分が添加され商品化されているのです。だから、それらは概ね安い価格で手に入れることが出来ます。まさに“消費者の強い味方”として支持されてきました。でも、人間が作り上げた偽物でもあるかもしれません。本当に必要なものだけが加味されている食品の美味しさを舌に覚えさすことが大切なのです。 |
| |
今、数々の添加物が人体へ及ぼす悪影響を訴える本が次々と上梓され、本来のシンプルな食材、食品を見直そうという機運が高まっています。
古来の人たちが口にするのは、原食材そのものに火を入れただけのものだったと思われますが、食の味わいの楽しさを追求するにつれ、いろいろな調味料や加工品が開発されてきました。これらは食生活を豊かさにするもので、人間だけが手に入れた贅沢といえるでしょう。でも、あまりに人工の味が加味されて、本来の食材の味わいを見分けられなくなるといった現象も危惧しなければなりません。 |
| |
| “本物”は確かにあるのです。ただ、それを手に入れるには、多少の努力と知識とお金がかかることを覚悟する必要があります。 |
|
| |
| |
| |
 |
| |
| 【第15回】 [ 食育の重要性 (1) ] |
| |
| 人間の歯は上下で28本(親知らずをのぞいて)。3歳前後になると乳歯が20本生え揃い、6歳頃から順次、永久歯とはえかわります。中学生くらいになって完成するのが通常です。その永久歯が欠落している子供が増えているとの名古屋の歯科医師の調査結果が、以前に新聞に掲載されていたことがありました。 |
| |
一般的に永久歯の欠落は千人に一人の割合で先天的に起こりますが、調査結果では、永久歯が1,2本不足している子供が平均7%前後存在しているとか。
明確な理由は分かりませんが、除草剤が影響しているとの見方があるのです。植物の成長を促す遺伝子を阻害する、グリホサートという成分を含む除草剤が、人体にも悪影響を及ぼしているのではないかというのです。 |
| |
| 子供の病気には、栄養のバランスのくずれによる他、農薬や食品添加物が原因となっているとの、様々な指摘、警告がなされています。永久歯の欠落についても、可能性が無いとは言い切れません。人間が豊かにいっぱい食べることを 欲し、その欲求に応えようとすれば、大量効率農法、すなわち農薬や除草剤に頼らざるを得ず、結果として人体への様々な影響を及ぼす可能性が出てきたのは皮肉としか言いようがありません。 |
| |
 人間は、食べないと生きていけません。点滴だけでも命は保つことはできますが、口から食べて、内臓で消化して栄養を吸収し、エネルギーに変えることでこそ、人間らしく活動していけるのです。生きるための、もっとも大切な作業? ともいうべき”食べる”ことの重要性は非常に強いはずです。それには子供の頃から、本物の食べ物に出会い、本物を見る目を養っていくことが望まれます。 大人であっても、今からでも遅くありません。”食育”は、子供の食教育にとどまらず、私たち大人も関心を高め、豊かな食生活を目指すための活動として、 真剣に考えていかなければならない”育”なのです。現在の様々な食事情の流れ、子供の食の現状などの中から、食育の重要性を考えていきたいと思います。 人間は、食べないと生きていけません。点滴だけでも命は保つことはできますが、口から食べて、内臓で消化して栄養を吸収し、エネルギーに変えることでこそ、人間らしく活動していけるのです。生きるための、もっとも大切な作業? ともいうべき”食べる”ことの重要性は非常に強いはずです。それには子供の頃から、本物の食べ物に出会い、本物を見る目を養っていくことが望まれます。 大人であっても、今からでも遅くありません。”食育”は、子供の食教育にとどまらず、私たち大人も関心を高め、豊かな食生活を目指すための活動として、 真剣に考えていかなければならない”育”なのです。現在の様々な食事情の流れ、子供の食の現状などの中から、食育の重要性を考えていきたいと思います。 |
|
 |
| |
| 【第14回】 [ 食の安全意識の高まり(8) ] |
| |
 安全な食材供給のための方策は、かつてになく行政も力を入れはじめています。これも、消費者の安全への要求の高まりあってのことでしょう。 安全な食材供給のための方策は、かつてになく行政も力を入れはじめています。これも、消費者の安全への要求の高まりあってのことでしょう。
そして、安全な野菜や果物を供給すべく〔ポジティブリスト制度〕が5月からスタートしました。野菜や果物に残っている農薬の規制を厳しくしましょうというものです。 |
| |
| どう、厳しくなったのでしょうか。従来は、数ある多くの農薬のうち、残ってはいけないものとして283種類(農薬250、動物用医薬品など33)の使用基準が決められており、それを守っていれば良かったのです。しかし新しい制度では、原則としてすべての農薬を対象にして許容基準値を設定。基準値以上の農薬が残留していた場合は、店での販売が禁止されます。 |
| |
|
詳しく言えば、世界中で使用されている農薬のうち、799種を選び基準値を設け、それ以外のものについては、0.01ppm以上残留してはいけなくなりました。これは、かなり高い安全度だと思われます。増えた指定農薬の基準値は、〔コーデックス委員会〕(世界中で食べられている食品の安全についての規格を決定する委員会)の基準などを参考にして決められました。
|
| |
| 4年前の中国産の冷凍ホウレンソウから基準値を大きく超えた農薬が検出されたことや、消費者の不安感が広まったことが、この新制度の発足につながったとも言えます。生産する側も、今後ますます厳しい対応を迫られることになりますが、やはり、人間の口に入るものです。赤ちゃんからお年寄りまで野菜や果物を安心して食べられるのは、何ものにもかえがたいのではないでしょうか。 |
|
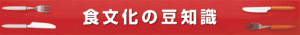 |
| |
| 【第13回】 [ 食の安全意識の高まり(7) ] |
| |
| その食品に入っている原材料そのものの表示をきちんと見て、購入の判断めやすにすることは大切です。原材料は、重量割合の多い順に記載されています。 |
| |
たとえば、人気の高い酢風味のさっぱりドレッシング。原材料のトップには、果糖ぶどう糖液糖とあります。その次に醸造酢。口当たりをよくする目的もあるのでしょうが、少し腑に落ちません。そして、多くのチョコレートのトップ原材料が、カカオではなく砂糖となっています。その分、価格的には、高級チョコレートより安めですが、これも納得出来かねます。
原材料が、小麦粉、ソバ粉の順になっている、日本ソバを見かけることもあります。普通、ソバを購入する時は、ソバ粉がメインと誰もが思うでしょうが、市場では、そうとは限らないのです。お菓子のおかきでも、最初にうるち米やもち米が原材料として書かれていないケースも、まれではありません。 |
| |
|
原材料の重量度合いは、結局のところ、その商品を幾らで売るか、そのためには原価を幾ら掛けられるか、によるとも言えるでしょう。価格競争が激化する中、いかに安く消費者に提供できるかが、企業の命運を左右する時代です。 安い原材料を多く組み合わせ、添加物を加えることにより、それ風の商品に仕立て上げるテクニックが、一概に悪いとは言えません。現に、多くの消費者がそれらを買っているのですから。価格の安さが魅力です。
|
| |
| 本来の原材料で、シンプルに構成されている食材商品の方が価格的に高いケースが多いのは、悩ましい限りです。でも、あるべき本物の原材料からなる食品を一度、口にすると、その差は歴然です。まず、後口がよい。妙に甘くない。本物の味の自然の濃さを、自分の味覚基準にきちんと覚えさせて食生活を豊かにすることが、何よりも大切だとは思いませんか? |
| |
| |
|
| |
 |
| |
| 【第12回】 [ 食の安全意識の高まり(6) ] |
| |
加工食品の原産地や原材料表示の規制が徐々に厳しくなってきたのは、消費者にとっては安心できることですが、業者側は、対応に追われ、また自社の姿勢・スタンスをどこに置くかという決定が問われることでもあるのです。
今まで既に、国産にこだわり、輸入品でも上質の食材にこだわってきたところは、表示義務はむしろ歓迎できるでしょう。堂々と材料を表明できるからです。
逆に、原材料が海外産にもかかわらず、日本で加工することで国産と称して市場に出していたところは、品目によってはそれがかなわなくなります。 |
| |
| 漬物を見てみましょう。らっきょの漬物。原料原産地に国産と記載してあるのは、日本のらっきょを日本で加工していますが、原料が他国の場合は、それを明記しなけれがなりません。 |
| |
|
合びきミンチはどうでしょうか。以前は、ミックス肉の場合、表示の必要がなかったのですが、これからは50 % 以上を占める食材は原産地を記載しなければならなくなりました。ただ、豚肉60%牛肉40 % の場合などは、豚肉のみ記載すればいい。人気のあるブランド豚をもってきて表示し、牛肉は安い輸入肉を使っても表示せずにすむわけです。でももし、牛肉も国産を使用しているなら、国産牛と表示するでしょう?
|
| |
| また、生ハンバーグは、合びきミンチに塩を加えて練りこんだだけのものなら、原材料表示は必要ですが、それに卵やパン粉などを加えると、複雑な加工品になるので、表示の必要はなくなります。 |
| |
 ジャムは、まだ原材料産地の記載義務はありません。だから原産国日本とあっても、国産のいちごや柑橘類を必ずしも使っているとは限らないのです。でももし、国産の柑橘類を使用した物なら、○○県産とか○○農園のもの、と記載するでしょう? ジャムは、まだ原材料産地の記載義務はありません。だから原産国日本とあっても、国産のいちごや柑橘類を必ずしも使っているとは限らないのです。でももし、国産の柑橘類を使用した物なら、○○県産とか○○農園のもの、と記載するでしょう?
食表示の公正化を促進するために、まず原材料産地をチェックして、自分が望むものを購入するという姿勢が消費者に強まれば、さらに,表示義務意識の高まりは増してくるのではないでしょうか。 |
| |
|
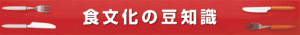 |
| |
| 【第11回】 [ 食の安全意識の高まり(5) ] |
| |
| さて、加工食品の場合の「原産地」の表示方法は、どうなのでしょうか。缶詰め、瓶詰め食品、味つけされた加工食品などは、加工された国が、原産地国と表示されます。従って、日本で加工された食品には、「原産国日本」と表示されている例は見かけません。パスタ、オリーブオイルなどの原産国はイタリア表示のもの、メープルシロップはカナダ表示、蜂蜜や果物缶詰めなどは、中国表示のものをよく見かけます。 |
| |
ただ、加工食品は、原材料と原産国とが必ずしも一致しないケースがあるのです。例えば、日本の醤油でも、アメリカ産の大豆を使用していることが多いですし、うどんも、オーストラリア産の小麦粉が原料のものがあります。ドイツのソーセージでも、イギリスの肉が原材料になっていることもあるのです。
“紀州和歌山の梅”を買って食べても、実は中国産の梅かもしれない。”浜松のうなぎの蒲焼き”も、実は中国産のうなぎだった。今まではこのような加工食品が多く存在していました。 |
| |
|
そこで、原料をきちんと知りたいという声を受けて、「原料原産地」の表示規制が整ってきたのです。まず、農産物漬物、うなぎ加工品、かつお削り節、野菜冷凍食品の 4 品目の、原料原産地表示が義務付けられました。そして 2004 年 9 月から 20 食品群に広がりました。お餅や緑茶、カット野菜、塩蔵野菜&果物、調味した食肉など、かなり広範囲にわたっています。 2006 年1 0 月に完全実施となります。業者もすぐには対応できないので、準備期間をもうけたというわけです。ただし、表示しなければならないのは、全体の重量の50%以上を占める単一の原材料で、その他のものは表示しなくてもよいことになっています。
|
| |
| この規制基準は、消費者にとっては歓迎すべきものですが、内容はとても複雑で、すべてを理解するのは大変なことです。また色々な規制には、必ずといっていいほど、抜け道があります。というより、抜け道をうまく見つけないと、死活問題になる業者も少なからずいるのです。だから、やはり消費者が自分の こだわり度合いを定めて、購入したいものを選別していくほか無いのかもしれません。次は、どのようなケースがあるのか、考えて見たいと思います。 |
| |
| |
|
| |
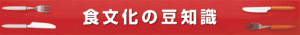 |
| |
| 【第10回】 [ 食の安全意識の高まり(4) ] |
| |
| ここ数年、輸入物が国産と偽られたり、国産でも人気の高い産地に偽装されたりする、食品の偽装表示が続発しました。新聞にも大きく取り上げられ、批判が高まるのを受けて、農林水産省も業者寄りから、消費者寄りへと、表示規制を少しずつ改善してきています。 |
| |
| まず「原産地表示」というのがあります。その名の通り、どこで作られたかを示す表示です。表示方法は、生鮮食品と加工食品では異なります。生鮮食品の中の野菜や果物などは、まずは原産地表示を信頼していいのではないでしょうか。和歌山のみかん、青森のりんご、淡路島の玉ねぎ、京都の九条ねぎ等です。 |
| |
|
 同じ生鮮食品でも魚や肉などは少し複雑です。それらは生きて移動するからです。魚は漁獲された水域の表示が義務付けられています。太平洋、日本海、アラスカ沖、などの表示を見たことがおありでしょう。鮪の刺身を買った時、原産地表示を見ると”太平洋産”とありました。広ッ!という印象です。でも、どこで獲れたか不明な場合は、水揚げされた港や、港がある都道府県の 表示でも良いとされています。ややこしいでしょう? 同じ生鮮食品でも魚や肉などは少し複雑です。それらは生きて移動するからです。魚は漁獲された水域の表示が義務付けられています。太平洋、日本海、アラスカ沖、などの表示を見たことがおありでしょう。鮪の刺身を買った時、原産地表示を見ると”太平洋産”とありました。広ッ!という印象です。でも、どこで獲れたか不明な場合は、水揚げされた港や、港がある都道府県の 表示でも良いとされています。ややこしいでしょう?
他の場所で獲れても、がんばって船を焼津港につけて水揚げすれば、全国的に人気の高い”焼津産”と表示できるのです。魚介類が2ヶ所以上で育てられた場合は、原産地は、より長く育てられた場所になります。あさり、鰻などは、外国生まれでも、日本での生育がより長ければ”国産”です。表示以外に、流通の詳細を知る手だてはありません。
|
| |
| 肉も、同様に一番長く飼育された場所が原産地となります。日本で生まれ、日本で育った牛でなくても、外国から生きた牛を輸入して、その時の年齢以上長く日本で飼育すれば、その牛肉は”国産”になるのです。 |
| |
| つまり、原産地表示は、規制通りに表示されていても、こと細かな出自を知ることは、困難な場合が多々あるのです。あまり神経質になっても、食品選びに疲れてしまいますし、正確に確かめるなら DNA 鑑定という手もありますが、そんなこと簡単には出来ませんよね。 |
| |
| となると、私たち消費者は、ただ信じ込むのではなくて、色々分かりにくいこともあるのだという認識をもって、原産地表示を見ましょう。信頼できる店を選ぶことも大切です。 |
| |
|
| |
| |
 |
| |
| 【第9回】 [ 食の安全意識の高まり(3) ] |
| |
| 食品の安全性への関心が高まるにつれ、食品加工分野でも、有機栽培原料を 使用したものが人気を集め出しています。最近のスーパーマーケットでも、 有機味噌、有機醤油等を見かけることが多くなりました。価格は少し高めです。 |
| |
 お酒でも、オーガニックビールや有機酒が出てきています。オーガニックビールとは、原料となるモルトやホップも有機栽培のものであることが条件となっており、国内ではまだ殆ど生産されていないため、アメリカやドイツから調達する必要があります。よって、ポピュラーに市場に出回るのは、まだ先のことになるでしょうが、一般に販売されるのが待ち遠しい気がします。 お酒でも、オーガニックビールや有機酒が出てきています。オーガニックビールとは、原料となるモルトやホップも有機栽培のものであることが条件となっており、国内ではまだ殆ど生産されていないため、アメリカやドイツから調達する必要があります。よって、ポピュラーに市場に出回るのは、まだ先のことになるでしょうが、一般に販売されるのが待ち遠しい気がします。 |
| |
| 同じ酒でも、国産の米やさつまいもなどを使用する清酒や焼酎の有機酒は、かなり浸透してきました。有機栽培の米「あきたこまち」を使った日本酒や、有機栽培のさつまいも「黄金千貫」を使った焼酎などが、食の安全志向を追い風に頑張っているようです。そうそう、有機ワインも見かけるようになりました。 これからの有機食品の課題は、いかに美味しさを極めることが出来るか、です。 いくら健康に良いといっても、美味しくなければ、うれしくありません。 |
| |
| 自然食・食事法で名高い「マクロビオテイック」料理は、基本的に自然農法や有機栽培で取れた野菜を中心にした食事で、砂糖の替りにはメープルシロップなどを使用、米も玄米が基本です。なんだか、健康には良さそうだけれど、、、なんて、思う方もいらっしゃるでしょうが、素材そのものの味が深く、予想をはるかに越えて美味しいものです。 |
| |
| 有機酒も、マクロビオテイック料理も、手間がかかるという点では同様で、まだ市場の多くを占めるには至りませんが、確実にニーズ゙の後押しを受けて、伸びてくるでしょう。多少価格が高めでも、購入する人は増えてくると思います。 |
| |
|
 |
| |
| 【第7回】 [ 食の安全意識の高まり(1) ] |
| |
このところ、産地偽装や食品の不正表示などが次々と発覚し、食品への不信が高まっています。何を信頼すれば良いのか、利用者も困惑している状態でしょう。特に今は健康志向の時代です。食に対する関心は強いといえます。
また、食生活が健康にもっとも大きな影響を及ぼすことは、だれしもが知っています。健康をそこなうのは間違った生活習慣にありと、連日テレビや新聞でも伝達されています。 |
| |
 利用者の「食の安全」への関心が強まるのと平行して、色々な法改正がなされました。カナダやフランスなどでは十数年以上も前から導入されている有機食品の認証制度が、日本でも2001年4月からやっと開始されました。化学製品の肥料や農薬ではなく、自然の土壌を生かした有機農法。内容は、農薬や化学肥料を2年以上(果樹、茶などの多年生作物は3年以上)使用しないで作られた作物を、 JAS (日本農林規格)法に基づいて有機農産物と認める、というものです。認定されたものにだけ、有機 JAS マークがつけられます。 利用者の「食の安全」への関心が強まるのと平行して、色々な法改正がなされました。カナダやフランスなどでは十数年以上も前から導入されている有機食品の認証制度が、日本でも2001年4月からやっと開始されました。化学製品の肥料や農薬ではなく、自然の土壌を生かした有機農法。内容は、農薬や化学肥料を2年以上(果樹、茶などの多年生作物は3年以上)使用しないで作られた作物を、 JAS (日本農林規格)法に基づいて有機農産物と認める、というものです。認定されたものにだけ、有機 JAS マークがつけられます。 |
| |
この認証制度発足により、認定を受けない食材を有機○○と売り込むのは、違法となりました。以前、有機野菜と銘打って売られていた食材が果たして本当にそうだったのかは、今となっては私たちには推し量るすべはありませんが、現在の有機 JAS マークのついた農産物が信頼に値するのはうれしいことです。
ちなみに、有機加工品とは、原料として有機農産物が95%以上を占めるものをいいます。 |
| |
| 食の安全チェックシステムと、正確表示への動きは、様々な食材に様々な形であらわれてきています。利用者も正しい知識と、本物を見抜く目を鍛えていくことが大切です。それが良心的な企業や作り手を育てるバックボーンとなることでしょう。 |
|
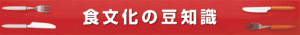 |
| |
| 【第8回】 [ 食の安全意識の高まり(2) ] |
| |
疑わしい人に、可能性のある人を加えると、全国で1400万人があてはまるだろうと言われている糖尿病は、一向に減る気配を見せていないようです。
予備軍も含めて、40歳以上の4人に1人が罹患しているといった状況の中、心配されるのは若年化です。最近、若者の糖尿病が増えているという話を新聞などでもよく取り上げています。 |
| |
| 当然、食生活の変化が影響しているのは言うまでもありませんが、気をつけなければならいのは、清涼飲料水の飲みすぎです。喉が渇いたときに、口当たりの良い甘い炭酸飲料や、スポーツドリンクをぐいっと飲んだ経験は誰にでもあるでしょう。確かにその爽やかな飲み心地は、直後の満足感を高めます。ただ、多く含まれている糖分の作用で、血糖値があがり、しばらくするとさらに喉が渇いてしまう、そして結果として毎日2~3リットルも飲んでしまう、といった異常な状態が続くと、立派な糖尿病予備軍です。血糖値があがりすぎて意識が朦朧として倒れてしまう、といったこともまれではありません。 |
| |
| おおよそ、清涼飲料水100ミリリットルには、10~12グラムの糖分が含まれています。1リットル飲んだら100グラムの糖分を摂取することになります。ならば、低カロリー商品?糖質の代わりにステビアやアスパルテームが使用されており、砂糖ではありませんので、エネルギーにはなりませんし、糖分過多にもなりません。虫歯の原因も作りません。でも、添加物には違いが無いのです。その安全性が完全に証明されているとは限りません。 |
| |
| 要は、大量に摂取しないことに尽きます。すかっとした飲み口の清涼飲料水はまさに清涼剤として楽しめばいいと思いますが、度を過ぎると、身体にとっていいわけはありません。大量に水分がほしいときは、やはり水を飲むのが無難というものです。 |
| |
|
| |
| |






 人間は、食べないと生きていけません。点滴だけでも命は保つことはできますが、口から食べて、内臓で消化して栄養を吸収し、エネルギーに変えることでこそ、人間らしく活動していけるのです。生きるための、もっとも大切な作業? ともいうべき”食べる”ことの重要性は非常に強いはずです。それには子供の頃から、本物の食べ物に出会い、本物を見る目を養っていくことが望まれます。 大人であっても、今からでも遅くありません。”食育”は、子供の食教育にとどまらず、私たち大人も関心を高め、豊かな食生活を目指すための活動として、 真剣に考えていかなければならない”育”なのです。現在の様々な食事情の流れ、子供の食の現状などの中から、食育の重要性を考えていきたいと思います。
人間は、食べないと生きていけません。点滴だけでも命は保つことはできますが、口から食べて、内臓で消化して栄養を吸収し、エネルギーに変えることでこそ、人間らしく活動していけるのです。生きるための、もっとも大切な作業? ともいうべき”食べる”ことの重要性は非常に強いはずです。それには子供の頃から、本物の食べ物に出会い、本物を見る目を養っていくことが望まれます。 大人であっても、今からでも遅くありません。”食育”は、子供の食教育にとどまらず、私たち大人も関心を高め、豊かな食生活を目指すための活動として、 真剣に考えていかなければならない”育”なのです。現在の様々な食事情の流れ、子供の食の現状などの中から、食育の重要性を考えていきたいと思います。 安全な食材供給のための方策は、かつてになく行政も力を入れはじめています。これも、消費者の安全への要求の高まりあってのことでしょう。
安全な食材供給のための方策は、かつてになく行政も力を入れはじめています。これも、消費者の安全への要求の高まりあってのことでしょう。  ジャムは、まだ原材料産地の記載義務はありません。だから原産国日本とあっても、国産のいちごや柑橘類を必ずしも使っているとは限らないのです。でももし、国産の柑橘類を使用した物なら、○○県産とか○○農園のもの、と記載するでしょう?
ジャムは、まだ原材料産地の記載義務はありません。だから原産国日本とあっても、国産のいちごや柑橘類を必ずしも使っているとは限らないのです。でももし、国産の柑橘類を使用した物なら、○○県産とか○○農園のもの、と記載するでしょう?

 お酒でも、オーガニックビールや有機酒が出てきています。オーガニックビールとは、原料となるモルトやホップも有機栽培のものであることが条件となっており、国内ではまだ殆ど生産されていないため、アメリカやドイツから調達する必要があります。よって、ポピュラーに市場に出回るのは、まだ先のことになるでしょうが、一般に販売されるのが待ち遠しい気がします。
お酒でも、オーガニックビールや有機酒が出てきています。オーガニックビールとは、原料となるモルトやホップも有機栽培のものであることが条件となっており、国内ではまだ殆ど生産されていないため、アメリカやドイツから調達する必要があります。よって、ポピュラーに市場に出回るのは、まだ先のことになるでしょうが、一般に販売されるのが待ち遠しい気がします。 利用者の「食の安全」への関心が強まるのと平行して、色々な法改正がなされました。カナダやフランスなどでは十数年以上も前から導入されている有機食品の認証制度が、日本でも2001年4月からやっと開始されました。化学製品の肥料や農薬ではなく、自然の土壌を生かした有機農法。内容は、農薬や化学肥料を2年以上(果樹、茶などの多年生作物は3年以上)使用しないで作られた作物を、 JAS (日本農林規格)法に基づいて有機農産物と認める、というものです。認定されたものにだけ、有機 JAS マークがつけられます。
利用者の「食の安全」への関心が強まるのと平行して、色々な法改正がなされました。カナダやフランスなどでは十数年以上も前から導入されている有機食品の認証制度が、日本でも2001年4月からやっと開始されました。化学製品の肥料や農薬ではなく、自然の土壌を生かした有機農法。内容は、農薬や化学肥料を2年以上(果樹、茶などの多年生作物は3年以上)使用しないで作られた作物を、 JAS (日本農林規格)法に基づいて有機農産物と認める、というものです。認定されたものにだけ、有機 JAS マークがつけられます。