「食文化の豆知識」カテゴリーアーカイブ
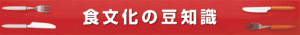 |
| |
| 【第6回】 [ 遺伝子組み換え食品 ] |
| |
| 最近、[遺伝子組み換え食品]という言葉をよく耳にしますが、これは、本来の遺伝子の配列に手を加え、病気や害虫、農薬に強い性質へと人工的に変えた食品を指したものです。日本では商業用に栽培はされていませんが、米国では多くの作物に適用されています。 |
| |
| そのうち、日本への輸入が認められているのは、大豆、じゃがいも、とうもろこし、菜種、綿などで、2001年からこれらの遺伝子組み換え食品に、その旨の表示が義務づけられました。加えて、遺伝子組み換え農産物を原料とした加工品でも、原材料に占める割合が多く(3番目まで)、かつ全重量の5%を占めるものも、表示が義務づけられています。逆に、使用していない、といった表示は任意となっていますが、豆腐やスイートコーンに、”遺伝子組み換えではありません”などと表示されている場合が多いのは、やはり安全ではないのからなのかと、少し気になりますね。 |
| |
元気な作物を大量に生産する方法としては、確かに理にかなっているかもしれません。遺伝子を組み換えることで、効率的な収穫が可能になるのですから。
折角手をかけて育てても、病気や害虫にやられたり、農薬に耐え切れず枯れてしまったりして商品価値が無くなるロスを回避できる、画期的な方法ともいえます。遺伝子工学は、いろいろなことを可能にする夢の扉ともいわれています。ただ、本来の性質を遺伝子操作で人為的に変えられた農産物は、以前とまったく同じものなのか、食べ続けても何の影響もないのか、に対する答えはまだ出ていません。食を選ぶのも、人生を左右する重要なファクターでもあるのです。 |
| |
| |
| |
|
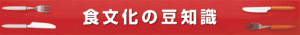 |
| |
| 【第5回】 [ 期限表示 ] の見方 |
| |
| ここ数年、食品の安全への関心がとみに高まってきています。様々な生活習慣病といわれる症状の発生は、食生活環境に所以する場合が多いといわれています。また、頻発した食品業者による産地不正表示や輸入野菜の農薬残留事件などが、いやが上にも、食への関心を引き起こしました。いまや、私たちは安全で豊かな食生活を送るために、自己防衛的に正しい知識と選択を持っていかねばなりません。 |
| |
食品に記された期限表示も、その期限までの安全を保障しているという意味で、正確に理解する必要があります。期限表示には、[ 消費期限 ] と [ 賞味期限 ] の2種類があるのは良くご存知ですね。[ 消費期限 ] は、この期限内に必ず食べてください、というメッセージです。肉や魚、惣菜の弁当など、品質が変化しやすい食品につけられています。[ 賞味期限 ] は、この期限内なら美味しく安全に食べられますよ、という意味です。つまり、賞味期限は、多少は過ぎても、まあ大丈夫。
ただ、[ 消費期限 ] にしても [ 賞味期限 ] にしても、表示された条件下での開封前の期限で、いったん包装をあけてしまったら、できるだけ早く食べてしまうのが安全です。 |
| |
| 昔は、あまりこういう [ 期限 ] は、目にしなかったような気がします。添加物の入っていない生の食品を使うことが多く、まだ食べられるかどうか、食べて安全かは、嗅覚と味覚、視覚をフル回転して判断すれば、まず間違いはなかったのです。ところが、様々な食品があふれ、保存性を高めるための防腐剤などの添加物が、人間本来の感覚の能力では判断しかねる状況を招いたといっても過言ではないでしょう。でも、今からでも遅くはありません。食品の本当の味を五感でキャッチし,安全性を判断できるための正しい選択眼を養っていくのに、遅すぎるということはありません。これから、安全な食べ物を楽しめるための豆知識をご提案していきたいと思っています。 |
| |
| |
| |
|
 |
| |
| 【第4回】三里四方の野菜を食べる |
| |
全国津々浦々にある郷土料理や伝統料理は、その土地で育てられ、収穫された食物をいかに有効に美味しく食べるかという知恵に基づいて、その土地の人々に親しまれてきたといっていいでしょう。鹿児島のさつま汁、熊本の辛子れんこん、島根の割り子そば、山口のふぐ刺し、奈良の柿の葉すし、富山のマスすし、秋田のきりたんぽ、、などなど、その土地ならではの名物料理は、枚挙に
いとまがありません。豊富なその土地の食物を、それぞれ、うまく生かし切る調理法を生みだしてきたのです。 |
| |
昔から伝えられている[三里四方の野菜を食べろ]は、まさに、郷土料理や伝統
料理の真髄を表す言葉です。その土地で収穫されたものを、その土地の調理方法で食することが、その土地に暮らす人にとっては、体に一番良いということ。勿論、今の日本では、全国の珍しいもののみならず、世界中の豊富な食べ物を手にいれることが可能で、それもまた私達の食生活を豊かにしてくれています。
でも、この[三里四方の野菜を食べろ]と良く似た言葉が多くあるのは、やはり、
その土地の気候風土に人間も馴染んでいるのだから、そこから取れる食物が
自然に体にも馴染むからではないでしょうか。 |
| |
[地産地消] 言葉通り、その土地で産まれたものを、その土地で消化するということ。[身土不二 しんどふじ] 身体と土は同じもの、ということです。
他に[域内消費] [土産土法] なども、ほぼ同じ意味です。
最近、この昔から伝えられてきた当たり前のことが、見直されてきているようです。余りにも贅沢になった食生活への反省やいましめなのかも知れません。
体に合い、口に合うのは、住んでいるところで取れたもの。
今さら、他の土地や外国産の美味しいものを食べるのはやめられないけれど、すぐ近くにある素朴な食べ物を見直してみるのも、本当のグルメなのかもしれません。 |
| |
 |
| |
|
 |
| |
| 【第3回】 「お節句」を楽しむ |
| |
| 日本では、季節の節目、節目に、さまざまな行事やしきたりが行われてきました。そのときどきの季節を精一杯に楽しむ知恵といいましょうか。春夏秋冬と四季がはっきりと移っていく日本ならではの習慣が、今もしっかりと受け継がれているのは、とても素晴らしいことではないでしょうか。 |
| |
| 中でも、節句は節日の記念日として、現在でも五節句が古くより伝えられています。1月7日に七草粥で新年を祝う「人日(じんじつ)の節句」、3月3日の「上巳(じょうし)の節句」 そう、桃の節句とか、ひなまつりとして今も華やかにちらし寿司などで、祝われていますね。5月5日は「端午の節句」 こいのぼりを飾り、柏餅やちまきを食べる習慣があります。子供の健やかな成長を祈るにふさわしい、みずみずしい新緑の季節の節句です。 |
| |
| 織姫、彦星で有名な7月7日の「七夕の節句」 も竹笹に願いをこめた短冊をかざる夏の風物詩として、広く親しまれています。最後は9月9日の「重陽(ちょうよう)の節句」 別名、菊の節句とも呼ばれています。先の4つの節句と比べると、一般にあまり祝われなくなりましたが、それは旧暦から新暦に移り、菊が咲くのには、早すぎる時期の節句になったからという説もあるようです。 |
| |
 いずれの節句も、その時々の花や食べ物を楽しむ、心豊かな生活シーンを彩ってくれるのです。節句をテーマに季節感あふれる料理で、自然と一体となる。そんな感性を持ち続けていたいものです。節分、お彼岸、月見、冬至などの日にも、それぞれ行事食がつきものです。ほんとうに、昔から日本人は、何かにかこつけて、旨いものを食べるのが好きだったのですね。 いずれの節句も、その時々の花や食べ物を楽しむ、心豊かな生活シーンを彩ってくれるのです。節句をテーマに季節感あふれる料理で、自然と一体となる。そんな感性を持ち続けていたいものです。節分、お彼岸、月見、冬至などの日にも、それぞれ行事食がつきものです。ほんとうに、昔から日本人は、何かにかこつけて、旨いものを食べるのが好きだったのですね。 |
| |
|
 |
| |
| 【第2回】 「おいしさ」とは |
| |
 よく「おいしい料理」といいますが、おいしさというのは、きわめて主観的な判断なのです。そこには、好み、という大きな要因が含まれているからです。 よく「おいしい料理」といいますが、おいしさというのは、きわめて主観的な判断なのです。そこには、好み、という大きな要因が含まれているからです。
おいしさは、味覚だけではなく、視覚、聴覚、嗅覚、触覚の五感で感じ取ると言われていますが、みなが同じように感じるわけではありません。濃い味付けが好きな人、薄味が好きな人、辛い料理が好きな人、あっさり系が好きな人と様々な好みがあり、同じ料理を食べても評価が分かれるのは当然のことです。結局は、食べる人の価値観や経験度合い、嗜好性で、おいしいかおいしくないかが決まるのです。 |
| |
ただ、味覚を含む五感は、ひとそれぞれ異なっても、おいしさの基礎条件、というものはあります。それは適温であること (冷たいものは冷たく、熱くあるべきものは熱く)、新鮮であること(発酵食材や干しものは別として)、それと安全で清潔であること、などです。
また、味には甘味、塩味、酸味、苦味という基礎4味があります。これに辛味、渋味なども加わります。
それらの絶妙な組み合わせが、うま味を引き出すといってもいいでしょう。甘さを強調しようと思うと塩をちょっと多くしたり、酸味を和らげるために砂糖を少し足したりとかで、味の混合効果を引き出すことができます。 |
| |
『好み』に大きく影響されるおいしさの判断基準ですが、うま味を感知する能力にたけた人も存在します。
繊細な舌の持ち主とでもいいいましょうか。
味覚を磨くには、経験がものをいいます。自分にとって何がベストな味なのかを極めるには、やはり上質と称される料理を試してみて、自分の味基準を高めていくことが、ほんもののグルメへの近道といえるでしょう。 |
| |
| 白菜のお漬物にお茶漬け、ってのも、やめられませんけどね。 |
|
 |
| |
| |
| 【第1回】日本料理の種類 |
| |
伝統的な日本料理には、さまざまな種類があります。「かいせき料理」、といっても懐石料理なのか,会席料理なのかで、まったく異なっているものなのです。
懐石料理とは、お茶席の際に頂く一汁二菜、一汁三菜といった軽い食事を指します。 |
| |
 一方、会席料理は、宴会などでお酒を楽しみながら頂く料理。だから日本料理店でのかいせき料理は、殆どが会席料理なのですね。ほかには、仏事の際の料理とされる、動物性の食材を使わず、植物性の食材で組み立てられた精進料理。ダイエット中の人にまさにピッタリの料理です。 一方、会席料理は、宴会などでお酒を楽しみながら頂く料理。だから日本料理店でのかいせき料理は、殆どが会席料理なのですね。ほかには、仏事の際の料理とされる、動物性の食材を使わず、植物性の食材で組み立てられた精進料理。ダイエット中の人にまさにピッタリの料理です。
また、今では余り見られませんが、一人ずつお膳にいくつもの料理を出してもてなす本膳料理などもあります。冠婚葬祭の時などに出されることもあります。地域性の高い料理としては、長崎が本場の卓袱料理(しっぽく)。円卓を囲み取り分けして食べるスタイルで中国料理の影響を受けています。
高知では、宴会では皿鉢料理が出てきます。冷たい料理も温かい料理も一緒に盛り込んだ、豪華でにぎやかな丸い大皿料理。聞けば、高知の人はお酒好きの人が多く、女性も例外ではなくお酒大好きなので、宴会では、お酒を落ち着いてじっくりと飲むために、どおんと、大皿を出しておいて、男性とさしで飲み勝負するんですって。 |
| |




 一方、会席料理は、宴会などでお酒を楽しみながら頂く料理。だから日本料理店でのかいせき料理は、殆どが会席料理なのですね。ほかには、仏事の際の料理とされる、動物性の食材を使わず、植物性の食材で組み立てられた精進料理。ダイエット中の人にまさにピッタリの料理です。
一方、会席料理は、宴会などでお酒を楽しみながら頂く料理。だから日本料理店でのかいせき料理は、殆どが会席料理なのですね。ほかには、仏事の際の料理とされる、動物性の食材を使わず、植物性の食材で組み立てられた精進料理。ダイエット中の人にまさにピッタリの料理です。

 よく「おいしい料理」といいますが、おいしさというのは、きわめて主観的な判断なのです。そこには、好み、という大きな要因が含まれているからです。
よく「おいしい料理」といいますが、おいしさというのは、きわめて主観的な判断なのです。そこには、好み、という大きな要因が含まれているからです。